毎日の仕事の中で、毎日どのような目的を持って仕事をしているだろうか?
また、目的達成のために何をしているだろうか?
1 京都旅行、1・2・3どれが良い旅行になりそう?
一つ目。皆さんですね。旅行に行くことになりました。とりえず京都に行くことだけは決まっている旅行。京都に行ってから考えようみたいな旅行です。
2つ目。京都で行く場所は決まっている旅行。金閣寺には行こう。清水寺には行こう。京都であのお店でご飯を食べようなどです。
3つ目。何のために京都に行き、何のために、何をするかが決まっている旅行。お友達との思い出を作りたい、歴史の理解を深めたいとか。何のために行き、何をするかが決まっている旅行です。
2 仕事における問い
仕事における目的を社員の方に伝えることで、どのような効果があると思いますか?
「この仕事はこのためにするんだ」「今回の仕事の目的は何だと思う?」「どうして会社がこういった取り組みをしてると思う?」伝えたり、共有したりすることで、どのような効果があると思いますか?
3 目的の重要性
目的という言葉を調べると「成し遂げようとする未来の良い状態」「何かを成し遂げたくて、それが未来において、こうなるといいな」という状態を指す。
仕事においては、目的を達成することが、仕事の成功といえる。仕事をこのためにやるんだとか、当社としては、このために事業を行っている。その目的を達成すると、仕事も成功しているといえる。
ついつい目的を忘れてしまって、具体的な行動をいきなり考えたり、とりあえず京都に行ってから考えようとか、してしまいがちなんですが、「そもそも何のためにやるのか?」「これって何のためにやるんだろう?」「そもそもどうなりたいのか?」「そしてどうなれば成功なのか?」という目的を設定したり、仲間と共有するということが、非常に重要です。
目的がある時とない時
目的がない時
「どうして成功したのか?」「成功していないのか?」「失敗なのか?そうでないのか?」判断がしづらい。「なんとなくうまくいった気がする」「前よりは良かった」目的が達成されたかどうかがわからない。
過去の経験や一般論から思考することが始まってしまいます。「いつもはこうしていた」「普通はこういうもんだよね」と考えがち。先ほどの、京都に行くとなった時に、大体みんなここにいくのここじゃない?前あそこに行って良かったから、もう一度そこに行こうよ。そんなふうに考えたり、逆に行ったことがあるから違うところに行きたい。等々。
そうすると、 Aさんはこんなこと言う。Bさんはこんなことを言う。Cさんは違うことを言う。と、全くまとまらないということがあります。
目的がないと、何のためにやっているかということがないので、淡々と行動したり、タスクをこなすだけ等、作業的になってしまいます。
目的がある時
「うまくいくのか行かないのか?」「うまくいったのか、いかないのか?」がわかる。成功失敗の判断基準ができる。
「こうなったらいいな」という未来の良い状態から、逆算して考えるので、あるべき状態から考える等、思考の順番ができます。
仲間同士で考えるとき、「こうなるためには何がいいだろう」等々、議論ができるので、立場が違う方とか、それまでの経験が違う方同士が、議論をして、議論の質が高くなる。
目的があると、そこを目指していく。
目指すということで、達成への意思が生じる。
仕事のやりがいにも繋がってくる。
目的があるとないとでは、大きく行動や成果が変わってくる。
営業活動やマネジメントにおける目的を一緒に考えてみよう
例えば、毎週行われている定例会議。何のためにやるんでしょう?そして、ワンオンワンミーティング個人面談。これって何のためにやるんでしょうか?いつもやってるからやっている会議、会社がやろうと言ったから行っている会議、あんまり意味がない。
例えば、毎週行っている定例会議。目的を設定すると「来週までの行動を決める」ために行うと、良い会議になりそうです。そして、お互いの取り組みを知って、助け合うために行っていると、他の方の発言にも耳を傾けたり、自分も協力を仰いだりします。また、マネージャーの方が、自分の言いたいことを言うためではなく、「社員との関係性の構築をするため」「悩んでいることを早く見つけたり、解決をするため」に行うと良いものになりそうです。
営業活動において
お客様の声がけはどうでしょう?
お客様にお声をかけるのは「営業の成果を出すため」?「ご契約いただくため」?「ある金融商品を買っていただくため」?そのような目的で声掛けをして、喜ぶお客様いらっしゃいますか?
社員の方に伝えるとしたら「来局してくださった方へ感謝を伝えよう」「感謝の気持ちを持って接しよう」「お客さまの話を聞いて差し上げよう」「これをきっかけに、お客さまとの関係性を構築していこう」 等の目的を伝えると、そのために声をかけるんだという意識で、行動して行きますので、行動の質が上がりそうです。
目的を持っているときと持っていないときは、仕事の質に大きな差が出ます。
当たり前になってやっていることとか、いつもやっていること、無目的になっているもの要注意。特に定例と付くものは、無目的になりがち。そして目的を共有することで、マネージメントがしやすくなります。
行動 1つひとつ指示をしたり見守ることってほぼ無理です。ですが、目的を伝えておけば、その目的に向かってくれるわけですから、目的が叶えられたかどうかで、判断できる。横にいなくても、離れていても、マネジメントがしやすくなります。
習慣化しよう!
1 目的を自分で設定する
誰かに目的を与えられていても、与えられなくても、目的を自分で設定する。
会社からこういったお達しがありました。っといったことがあっても、じゃあ自分だったら、どういった目的でやろうか?どういう目的だということを社員に伝えようか。を考える。
2 意見がまとまらない場合
他者との議論が散らばり、私はこれしたい。私はこれがいいと思います等、発散しそうになったら、目的に立ち返る癖を作ることです。
3 毎日目的を立てて振り返る
毎朝チームや自分の目的を立てて、仕事終わりに振り返るということ。
「今日はいい1日だったかどうか」といったことが、判断できます。
このように目的の重要性をですね。考えていただければ嬉しいです。

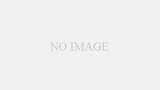
コメント